
|
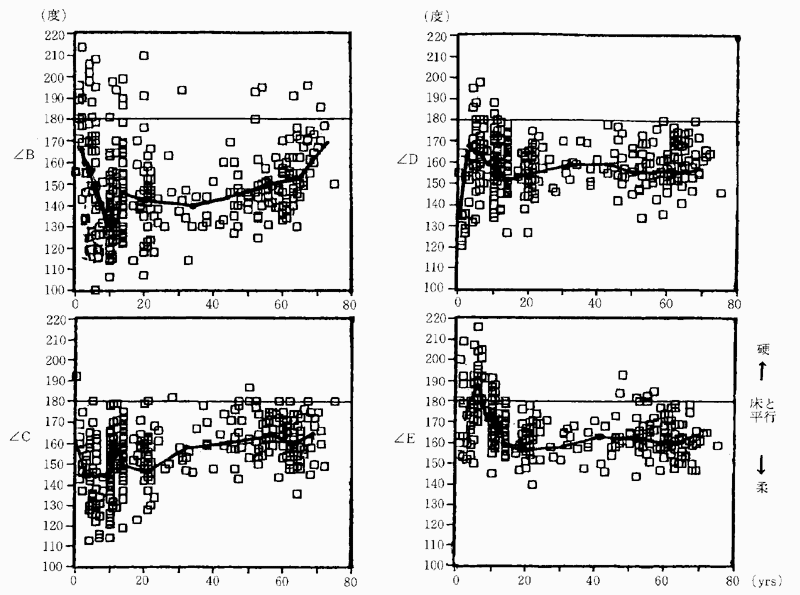
図16 伸展角、∠B、∠C、∠D、∠Eの年齢による変化。
(実線は各年代の平均値を結んだもの)。 辰の両方に関与している。そこで、押さえがなくなると、筋活動が上体および下肢の伸展に関与し、結果として上体の伸展度が減る事例で、成熟後に多くみられる。このこともまた、脊柱伸展の主動筋群が、加齢にともない尾方化することをしめすといえる。40歳以降についてみると、屈曲運動の場合と違い、運動習慣の効果はなく加齢退行がみられる。 乳児期は大人による腰の持ち上げで計ったため、腰部(D)を最大屈曲とする“くの字型”になり、その角度(f−I)平均は23度となり可動性は大きい。 (3) 脊柱の伸展・屈曲の関わり 脊柱の可動性を屈曲と伸展について『単一角度』の相関でみると、全体ではr=0.16で低い。 14〜29歳群を境に3群に別けてみると、14〜29歳群では、r=0.4(P>0.01)を最高に、それ以前はr=0.27、それ以後はr=0.01と低い。また40歳以降についてみると、運動習慣の影響は、上述のように屈曲度にはプラスの影響が推察されたが、伸展度にはみられなかった。これらを総合すると、屈曲運動と伸展運動の制約要因は、青年期をのぞき、かなり独自性があるといえる。日常の動作様式の観察から、中・高年期には“身をかがめる”動作は多いが、反らせるのはアクビくらいしかなく(未発表資料)、上体の捻転もすくない10)。そこで器質的な加齢退行に、運動習慣が相乗して、成熟後の両機能の差異をひろげたと考えられる。 (4) 脊柱の伸展・屈曲の年代特性 以上のことをまとめて年代別の特徴をみると、次のようになる。 乳児期外力を加えたり補助によって遂行で
前ページ 目次へ 次ページ
|

|